はじめに
日本は、いつから「帳簿で動く国」になったのでしょうか。
平安時代と聞くと、律令や制度、天皇や政治の歴史がまず思い浮かびます。
けれども、平安時代の木簡を読むと、まったく違う景色が現れます。
そこにあるのは、稲を集め、配り、運び、貸し、残りを数えるという、
とても地味で、しかし国家を動かすために欠かせない仕事の積み重ねです。
木簡とは、当時の役所や現場で使われていた仕事の札です。
物の出入りや作業内容、日付や人名を細長い木の札に書きつけ、
日々の業務を管理していました。
1200年前の年末年始、
その場所で、どのような仕事が帳簿につけられていたのか。
木簡の言葉に沿って、ひとつずつ見ていきます。
十月 ― 収穫のあと、帳簿が動き出す
弘仁元年十月二十日。
この木簡に残っている記録は、この日の稲の収納から始まっています。
木簡には、次のように書かれています。
弘仁元年十月廿日 収納稲事
合 一千五百九束
山田女佃 二町六段 千二百四十三束
凡海福万呂佃 四段
同 地子 六段 二百五十二束
ここに出てくる佃は荘の直営田、
地子は農民が納める地代です。
教科書にある租の制度が、
ここでは具体的な数量として処理されています。
そして、その日のうちに、
稲はもう動き始めます。
同日 下 廿束
葛木寺 進者
二十束が、葛木寺へ送られました。
宗教施設への支給も、
特別な行事ではなく、日常の出納のひとつとして処理されています。
計算を終えた時点で、この日の残りはこう記されています。
定残 一千四百八十九束
十月下旬 ― 働く人と物資の流れ
六日後、十月二十六日。
弘仁元年十月廿六日 下 卌七束五把
義倉籾一石四升料十六束
一束籾女功食料
二束運人功料
庄垣作料十五束
白米運夫功二束
小主并従経日食一束五把
合下 卌七束五把
残稲 一千四百四十一束五把
まず「義倉」は、飢饉や災害に備え、貧しい人々を救済するため、
貴族や官人、庶民から徴収した穀物(粟など)を貯蓄した倉庫制度です。
そこに収めるための籾が、十六束分、ここで確保されています。
次に現れるのが、働く人たちの食料です。
作業にあたる女性たちの食事に一束、
荷を運ぶ人の食事に二束、
さらに白米を運ぶ人の食事に二束が支給されています。
そのあいだに挟まれる「庄垣作料十五束」は、
この荘の囲いや施設を整えるための修繕費として、
十五束の稲が使われていることがわかります。
そして最後に、
この荘の管理を担う小主とその従者の
日々の食事として一束五把が支給されています。
これらをすべて合計した結果が、
合下 卌七束五把
であり、
この日の支出後の残りが、
残稲 一千四百四十一束五把
と記されています。
この日のすべての支出を処理したあとの在庫残高を明示しています。
この一行によって、この木簡が単なる記録ではなく、
きちんと計算された帳簿であることがはっきりします。
ここに並んでいるのは、制度の言葉ではありません。
備え、労働、運送、修繕、管理、そして食事――
人の暮らしそのものが、束と把という単位で、
この帳簿の中を流れています。
年末から正月へ ― 祭りと暮らしが帳簿に載る
この木簡の記録は、十二月に入り、
労働や運送の支出に加えて、
祭祀と正月の準備、そして人々の生活そのものが帳簿の中心に現れてくるのです。
まず、年末の核心部分となる記述です。
糯米舂料一束 酒〈〉
祭料物并同料菁奈等持夫功一束
依門成事太郎経日食二束
庄内神祀料五束
ここには、年末の空気が凝縮されています。
「糯米(もちごめ)」は、日常の飯米とは別の、特別な場面に使う米です。
それをつくための稲が支給され、酒が用意され、
祭祀のための物資と、それを運ぶ人々への支給が記されています。
さらに「庄内神祀料」とあり、
この荘の内部で神祭が行われていたことがわかります。
祭りは理念ではなく、
物資・労働・運送・配給の連なりとして、帳簿の中に現れています。
この時期、同時に記録されているのが出挙です。
出挙とは、国や荘が人びとに稲を貸し、
収穫後に利息をつけて返させる仕組みです。
人々出挙給十七束
凡海加都岐万呂十束
民浄万呂三束
建万呂妻浄継女二束
大友三月万呂二束
農民一人ひとりの名前と、貸し与えられた稲の量が並びます。
そして、年末の帳簿は、ある期間を切ってまとめられます。
小主并従経八日二束六把
自十二月廿日/迄廿七日
合下百八十七束九把
残稲一千二百五十三束六把
十二月二十日から二十七日までの支出を合計し、
残高を更新しています。
まさに「締め」の作業です。
年が明けて、弘仁二年正月二十六日にも、同じ帳簿の論理が続きます。
弘仁二年正月廿六日下百五十七束之中
…京持行人功食一束
…宮所庄持運車引建万呂六箇日
食并酒料三束
日別一升六合食/又酒日別一升
年が明けて、弘仁二年正月二十六日。
私たちが思い浮かべる「正月」は三が日ほどですが、
当時の「正月」は一か月近く続く新年の期間でした。
正月廿六日とは、年が明けてまだ新年の空気が色濃く残る頃です。
帳簿には、都へ向かう運送の記録が続きます。
荷を運ぶ人の食事として一束、
宮の用のため、この荘から物資を運ぶ仕事として、
建万呂が六日間、荷車を引き、
その間の食料と酒として三束が支給されています。
しかも配給量は一日あたり、
食が一升六合、酒が一升と、きちんと日割りで計算されています。
さらに年明け後も、一定期間でまとめて計算されています。
自正月廿日始迄二月三日
食稲四束二把
二郎并従一日半食六把
正月二十日から二月三日までの期間、
食料として稲四束二把が支給され、
二郎とその従者には一日半分の食事として六把が配られています。
1200年前の日本では、こうして人々の暮らしと仕事が、帳簿の上で静かに回っていました。
おわりに
この木簡に残っているのは、
英雄の物語でも、制度の理想像でもありません。
稲を集め、配り、運び、貸し、残りを数える。
祭りの準備をし、酒を配り、
働く人の食事を用意し、
正月になっても同じように帳簿をつける。
そうした一つひとつの仕事が、
一年という時間をつくっていました。
1200年前の人びとも、
今日の私たちと同じように、
月を区切り、日を数え、
手元に残った量を確かめながら暮らしていたのです。
木簡は、
当時の人びとが日々の仕事のなかで残した、
とても静かな記録です。
だからこそそこには、
歴史の教科書では見えない、
生きていた人びとの時間が、
そのまま刻まれています。

参考資料

本文中の解釈は、木簡本文と既存の研究例をもとにした、筆者なりの読みである。

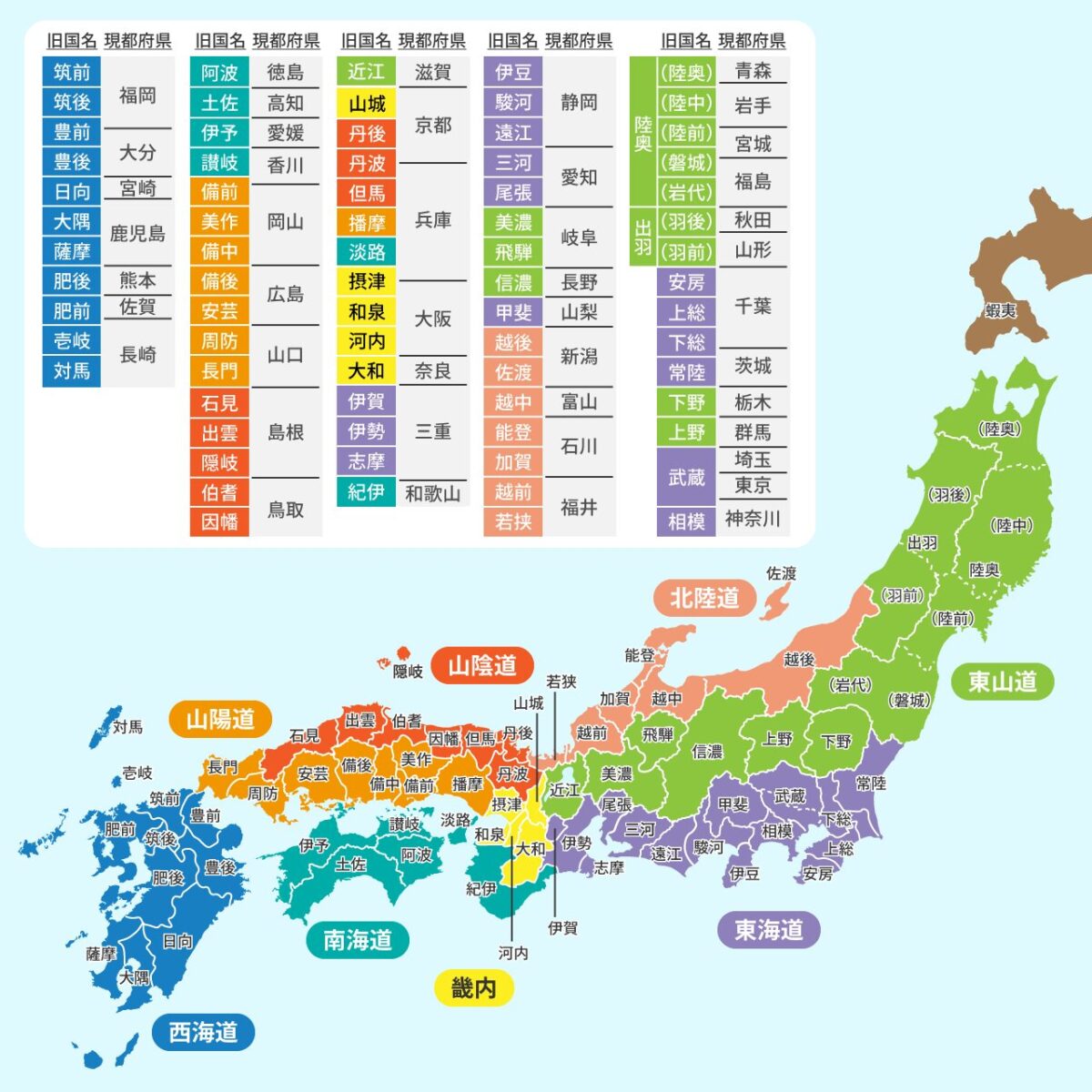
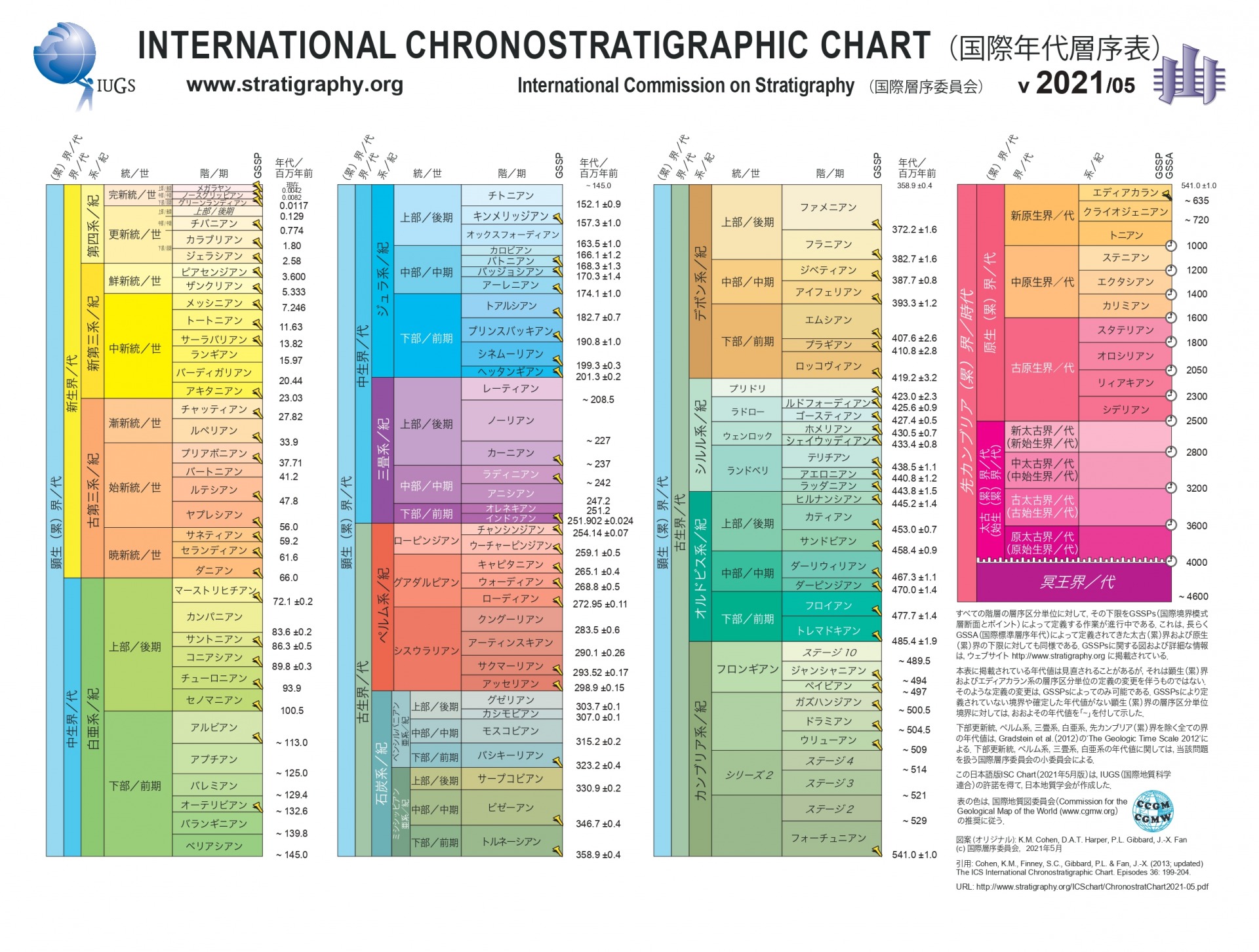






コメント