序章:海と山の交錯する地形の魅力
相模湾の浜辺から、背後に迫る山並みを見上げると、その奥に箱根外輪山の稜線が横たわっています。湯河原は、海と山がほとんど間を置かずに出会う土地。谷戸を縫うように人々の暮らしがあり、古くからこの自然の対峙は、信仰と交流の舞台でした。海辺では、磯や砂嘴(さし:岬や半島の先端から海に向かって細長く突き出た砂礫の州)で神を迎える祭祀が営まれ、航海や漁の安全、豊漁を祈る儀礼が繰り返されました。一方、外輪山の頂では、箱根駒ケ岳山頂の元宮や箱根神社に山の神・水の神を祀り、天候や五穀豊穣を願う山岳祭祀が続きました。
そして、この二つの祭祀を結んだのが、海辺から谷戸を抜け、奥湯河原を経て峠を越える古道でした。そこを行き交ったのは、漁師や農民、薬草を携えた山伏、遠くの出来事を伝える旅人たち・・・信仰と暮らしが交わる往還が、今も地形に刻まれています。
海の祭祀と集落文化
湯河原竹ノ花遺跡と滑石製模造品の祭祀的意義
湯河原町吉浜の竹ノ花遺跡は、古墳時代中期~後期(5~6世紀頃)に海辺で祭祀が行われた遺跡と考えられています。多数の土師器片とともに子持勾玉などの滑石製模造品(滑石を素材に実物を模して作った小型石製品)が見つかっています。遺跡は砂嘴(さし)で囲まれた静かな湾奥の岸辺に位置し、航海の安全や漁獲豊穣、あるいは背後の火山(箱根山)への畏怖などを祈る儀礼が営まれた可能性があります。実際、竹ノ花遺跡で検出された滑石製子持勾玉は古墳時代の神まつりの道具であり、柔らかい石材を加工して勾玉・有孔円板・剣形・臼玉などをミニチュアに作った石製模造品の一種です。これら石製模造品は古墳祭祀に伴うセットとして各地の祭祀遺構から出土するもので、竹ノ花遺跡の場合も内湾の砂州内部という立地からみて海上交通の守護を願う祭祀場だったと考えられます。伊豆半島・伊豆諸島には同時期の祭祀遺跡が数多く分布することが知られており(橋口尚武 1991『海と列島文化7: 黒潮の道』等)、竹ノ花遺跡もその一環として位置づけられる例と言えます。
真鶴三ツ石・羽根尾貝塚:海辺の聖所としての性格
真鶴半島先端の三ツ石(笠島)は、海中に三つの巨岩が突き出た景勝地で、そのうち二つの岩に現在も注連縄が張られています。これは当地の岩石が古来より海の神が宿る聖なる磐座として崇敬されてきたことを示すもので、現代でも元旦に岩間から昇る初日の出を拝む行事が続けられるなど、海と岩への信仰が色濃く息づいています。また、三ツ石にほど近い小田原市早川の羽根尾貝塚(真鶴町境界に位置)は縄文時代前期(約5,800年前)の大規模貝塚で、厚さ50cmほどの貝層からダンベイキサゴ・ヤマトシジミを主体とする貝殻のほか、カツオ・マグロ・イシナギ・イルカなど海洋性の魚類・海獣の骨、イノシシ・シカなど陸上動物の骨、クルミなど木の実、さらに漆塗り木製容器や丸木舟の櫂といった多様な遺物が良好な保存状態で出土しています。(坪田弘子編 2003『神奈川県小田原市羽根尾貝塚』発掘報告書)。注目すべきは、貝層中から成人男性の人骨が埋葬状態で発見された点で、貝塚が単なるゴミ捨て場ではなく墓地や祭祀の場として機能しうることを示す事例です
羽根尾貝塚の人骨埋葬は、縄文人が海辺の貝塚を聖域(魂の還る場)とみなしていた可能性を物語っており、海産資源への感謝や祖先・霊魂への信仰がうかがえます。
伊豆・相模湾沿岸における海の祭祀遺跡の事例
古墳時代~古代にかけて、伊豆半島や相模湾沿岸では岬の突端や離れ小島を舞台とした海の祭祀遺跡が多数確認されています。これらは集落から離れた海際の高所に土器や石製品を供献した露天祭祀で、漁業神や航海神を祀ったものと解釈されます。典型例の一つが静岡県下田市の夷子島(えびすじま)遺跡で、真鶴三ツ石と同様に海中から突き出た小島の頂上が祭祀の場となりました。昭和12年と34年に島頂の発掘調査が行われ、焚火跡とともに多数の手捏ね土器(土師器系土器)や須恵器片が出土しています。同様の岬祭祀としては、南伊豆町田牛の遠国島遺跡(オンゴクジマ。昭和期に頂上から奈良時代の土師器・須恵器片が出土)や、南伊豆弓ヶ浜のタライ岬遺跡(岬先端の崖下から古墳時代後期=6世紀頃の土師器・須恵器が多数検出)などが知られます。これらは概ね伊豆諸島や大島・三宅島などを遠望できる立地にあり、海の彼方の神々(航海・漁労の守護神)を祀る祭祀だったと考えられます(外岡龍二 1991「南伊豆の祭祀遺跡」所収)。
さらに伊豆半島北部でも、熱海市の宮脇遺跡(来宮神社・多賀神社境内)から古墳時代の三角縁神獣鏡など銅鏡4面が巨石下にまとめて埋納された遺構が発見されており(1958年調査、北澤宏明 2023『博物館研究報』による分析)、伊東市川奈の御笠山神社遺跡でも滑石製臼玉や土器片を伴う祭祀土坑が報告されています(桑原靖夫 1987「御笠山神社遺跡の調査」『考古学ジャーナル』)。以上のように、伊豆・相模湾沿岸には古墳時代~奈良時代を通じて海にまつわる祭祀遺跡が点在し、その存在は当時の海民社会における信仰世界を物語っています。
海産資源・貝塚に見る信仰上の意味
海辺の考古遺跡からは、食料資源である海産動物に対する特別な儀礼の痕跡も見出せます。縄文時代の貝塚ではイルカやクジラなど海獣類の骨が大量に含まれる例があり、それらの扱いには宗教的配慮があったと推測されています。考古学者・金子浩昌氏は、鎌倉市称名寺貝塚の発掘でイルカの頭蓋骨のみが単独で埋められた事例に注目し、縄文人が捕獲したイルカの霊を慰霊・供養する動物祭祀を行っていた可能性を指摘しています。実際、称名寺貝塚のほか横須賀市冑ケ台貝塚などでもイルカ頭骨の出土例が報告されており、縄文時代から海の恵みに対する感謝と畏敬が儀礼として表現されていたと考えられます。貝塚は生活廃棄物の集積所であると同時に、そこで消費された動物の魂を送り返す祈りの場でもあったのでしょう。
時代変遷と遺構配置からみた信仰文化の展開
湯河原・真鶴周辺から伊豆地域にかけての遺跡群を俯瞰すると、海と関わる信仰文化が時代ごとに形を変えつつ連続していたことが明らかになります。
縄文時代には集落近傍の貝塚が埋葬・祭祀の場となり(羽根尾貝塚の人骨埋葬など)、イルカ供養に見られるように狩猟採集民的な自然崇拝が行われていました。
弥生時代後期になると、砂丘上に方形周溝墓などの墓域が造成され集落と分離する傾向が現れます(伊豆河津町姫宮遺跡など)。
古墳時代に入ると、この地域では大型古墳がほとんど造られなかった代わりに祭祀遺跡や祭祀専用空間が各所に形成されるようになります。
伊豆半島では集落遺跡を発掘すると高頻度で祭祀用土坑や祭祀遺物集中が見つかり、なかには本来なら首長の古墳に副葬されるはずの銅鏡や勾玉が一般集落から出土する例も報告されています。この特異な現象から、伊豆の首長層は墳墓造営より神祀り(祭祀)に重きを置いた集団だった可能性が指摘されています。(金子浩之 2024年講演「伊豆の古代遺跡の分布的特徴」より)。以上のように、旧石器時代以降長きにわたり人々は海とともに暮らし、海辺の聖域で祈りを捧げてきました。その形態は縄文の貝塚祭祀から古墳期の岬祭祀、さらに神社境内での祭祀へと変遷しましたが、近年の考古学研究(地域の発掘調査報告や学術論文)によって、それらが一連の信仰文化の発展過程として連続していることが明らかになりつつあります。海から得られる恩恵と脅威に向き合い、それを超越的な存在に祈る――そんな古代人の祈りの営みが、湯河原・真鶴~伊豆半島の地には今なお多くの遺跡として刻まれているのです。
山岳祭祀と峠の信仰
箱根山・駒ヶ岳元宮の山岳信仰と神奈備信仰
箱根山(神山)と駒ヶ岳は古来より神霊が宿る山として崇められ、社殿建立以前の太古から山岳信仰の対象となってきました。神奈備信仰とは、山や森そのものを神の依り代(ひもろぎ)として祀る古代信仰であり、箱根の神山もまさに「神奈備(かんなび)」として扱われた例です。伝説によれば第5代孝昭天皇の時代(約2400年前)、仙人の聖占(しょうせん)が箱根山最高峰の神山に降臨する山神を感得し、その南隣の駒ヶ岳山頂に神仙宮を建立したのが箱根山祭祀の始まりとされています。続いて利行丈人・玄利老人という修行者たちが、神山を「天津神籬」(神が宿る神体)とし、駒ヶ岳山頂を「天津磐境」(祭祀の場)に定めて祀ったそうです。これらは後世の社伝的伝承ではありますが、箱根山において山自体を神体として崇敬する神奈備的な山岳信仰が極めて古い起源を持つ可能性を物語っています。
奈良時代の天平宝字元年(757年)、万巻上人が箱根権現(三所権現)を開き、神山の南麓・芦ノ湖畔の岬(現在の元箱根)に祭祀の場を移して箱根神社(里宮)と山麓の東福寺を建立しました。これにより箱根山の祭祀は神仏習合の寺社としての体裁をとるようになりますが、山頂の霊場(奥宮)への信仰自体はその後も脈々と続きました。
中世に入ると天台宗系の密教・修験道の影響で多くの修験者が箱根山に入り、箱根権現は関東有数の修験道霊場として繁栄しました。平安末期には箱根権現別当の行実が伊豆流人の源頼朝を支援し、鎌倉幕府成立後は武家の尊崇を集めています。このように中世までに箱根山信仰は広く崇敬される存在へと展開しました。
一方で信仰の源流はあくまで神山そのものへの畏敬であり、駒ヶ岳山頂では社殿を持たない古式の祭祀が続けられていました。駒ヶ岳山頂には古代から磐座(いわくら)による祭祀場が存在し、石を環状に配した「磐境」を設けて神体山・神山を遥拝する場としたと伝えられています。現在も駒ヶ岳頂上には「馬降石(ばこうせき)」「馬乗石(ばじょうせき)」と呼ばれる巨岩を中心とした磐座群があり、古来この場所で箱根山の神々を祀ったとされます。
以上のように、箱根山・駒ヶ岳の山岳信仰は、建築物を伴わない原初の神奈備信仰に始まり、奈良時代以降は神仏習合の社寺によって組織化され、中世には修験道の隆盛により関東を代表する霊場として発展していきました。
修験道における峠:湯河原~奥湯河原~箱根外輪山登拝路の宗教的意味と役割
修験道において「峠」は現世と霊域の境界をなす重要な地点であり、登拝者(山伏)が俗界から聖なる山へと入る結界として宗教的意味を持ちます。箱根山周辺では複数の峠道が存在していますが、その中でも相模湾岸の湯河原から奥湯河原を経て箱根外輪山に至るルートは、古くから修験者たちに利用された登拝路の一つと考えられています。伊豆・箱根エリア一帯(湯河原を含む地域)は関東山伏発祥の地とも称され、現在は分断されているものの、往時は伊豆権現(走湯山)と箱根権現を結ぶ修験道ネットワークが存在していました。湯河原から外輪山へ向かう峠筋は、まさに海岸の霊場(走湯権現=伊豆山神社)と山岳霊場(箱根権現)とを繋ぐ要衝であり、修験の行者たちが峠を越えて二所権現を参詣する重要な修行経路であった。
具体的に、湯河原背後の山地から箱根外輪山南部にかけては、古道や峠に修験的遺跡が点在しています。たとえば十国峠・日金山(標高776m)付近は、伊豆山権現の奥之院にも近く、修験道の行場として栄えた場所です。日金山山頂の東光寺は修験の寺院で、本尊は地蔵菩薩であるが、境内には三途の川や賽の河原を模した一角や水子地蔵群があり、修験道の死生観に基づく空間が造営されています。この東光寺から岩戸山・十国峠を経て湯河原温泉へ至る古道は「石仏の道」とも呼ばれ、沿道に苔むした地蔵尊や石塔が点在しています。こうした峠道の石仏群は、旅人や行者が峠で安全祈願・供養を行った名残であり、峠そのものが聖俗の境界かつ信仰の場であったことを示しています。修験道では峠に差し掛かる際、「六根清浄」の掛け声とともに一礼したり、道祖神・地蔵に手を合わせる習俗も伝わっています。峠越えはすなわち心身を清め別世界へ入る通過儀礼の場であり、湯河原~箱根外輪山の峠でも同様に宗教的な区切りとしての役割が果たされていたと考えられます。
湯河原からの古道と箱根信仰の交錯(峠・行場・水源との関係)
相模湾沿いの湯河原から箱根山に向かう古道は、海辺の温泉文化と山岳霊場を結ぶ信仰の道でもありました。この路沿いには峠だけでなく、修験者の行場(ぎょうば)や霊水にまつわるスポットが点在し、地域信仰圏を形成していました。湯河原周辺には複数の瀑布や洞窟があり、それらは修験道の行場として利用された形跡が見られます。代表的なのが湯河原町吉浜にある「しとどの窟(いわや)」です。源頼朝が石橋山の戦いに敗れた際に身を潜めた伝説で知られるこの洞窟は、実は山岳信仰や地蔵・観音信仰の聖地でもありました。中世以降、行者たちが籠もり滝行や座禅修行を行った場所とされ、洞窟内外に石仏や供養塔が安置されました。近世には地元の篤志家が洞窟内から地蔵像を発見し、禅廊上人が再興して地蔵堂を建立するなど、修験者の行場が整備され霊場として崇敬されていました。
また、水源との関係も見逃せません。湯河原は古来より温泉(湯治場)として知られますが、温泉そのものが霊場として機能していた例が箱根にはあります。箱根山中の姥子(うばこ)温泉は、室町時代に長安寺という寺院が置かれ、温泉霊場となっていました。源泉が湧出する岩には御神体のように注連縄が掛けられ、修験者の「湯垢離場(ゆごりば)」(入峯の前に穢れを落とすため温泉で身を清める場)として利用されてきました。江戸時代の資料にも姥子の湯は「禅定の湯」と記され、山伏が湯治修行する霊湯であったことがうかがえます。
湯河原温泉も開湯は奈良時代とも伝わる古湯であり、同じく修験道や温泉信仰と結びついていた可能性があります。湯河原には五大滝の一つ「不動滝」もあり、不動明王を祀るこの滝は修験者の滝行場として用いられたとの伝承があります。滝壺や湧水など清浄な水場は、修験道の行者にとって身を清める大切な修行ポイントであり、峠への途上にある水源は信仰上の意義を持ったことでしょう。こうした湯河原~箱根にかけての古道では、峠(境界の祭祀空間)、行場(修行の実践空間)、水源(浄化と再生の空間)が相互に関連し合い、海と山を結ぶ独自の地域信仰圏を形作ってきたのでしょう。
考古資料からみる山岳信仰の実証
箱根山の山岳信仰は、考古学的にも裏付けられます。駒ヶ岳山頂の箱根元宮跡(駒形権現社跡)では、昭和39年(1964年)の社殿再建工事に先立ち発掘調査が行われ、多数の祭祀遺物が出土しました。出土品には、土師器(はじき)の坏(つき)(皿)片が多数含まれ、口縁内側に油脂が付着したものも見つかっています。これは灯明皿として用いられた痕跡です。また宋銭(北宋銭)や寛永通宝といった古銭も発見されており、賽銭として供えられたものと推定されています。宋銭の国内流通は平安末期まで遡りますが、出土状況から本遺跡での使用時期は中世以降と考えられています。
湯河原~奥湯河原~箱根外輪山古道の歴史的・宗教的考察
古道の概要と歴史的背景
湯河原から奥湯河原を経て箱根外輪山へ至る古道は、相模湾沿岸から箱根山地へ向かう山道であり、旧石器時代から人々の往来があったと考えられる道筋です。考古学的には、約1万5千年前にはこの周辺で伊豆・鍛冶屋産の黒曜石を用いた石器生産が始まっており、湯河原町内の先土器時代・縄文時代遺跡からも伊豆産黒曜石製の石器が出土しています。黒曜石は当時の交易資源であり、縄文後期(紀元前2000年頃)になると湯河原周辺の黒曜石資源が採り尽くされ、人々は他地域へ移動した形跡があり、このことは太古の昔から伊豆(現在の熱海・湯河原一帯)と周辺地域を結ぶ移動経路が存在したことを示唆します。また、湯河原温泉自体も古くから知られ、奈良時代の『万葉集』には、湯河原の温泉が詠まれています。巻十四東歌に「あしがりの土肥の河内に出づる湯…」とあり、8世紀頃にはすでに渓谷から湧き出す湯河原の温泉が人々に親しまれていたことが分かります。このように先史時代から古代にかけて、湯河原の谷筋には人の営みと温泉利用があり、古道は資源交易や湯治・療養の目的でも用いられていたと考えられます。
中世に入ると、この古道は宗教的・軍事的にも重要な舞台となりました。治承4年(1180年)の石橋山合戦で敗れた源頼朝が、土肥実平の案内で逃れ、小舟で安房国へ落ち延びた逸話が残されています。頼朝が身を潜めたとされる「しとどの窟(いわや)」は標高535m付近の岩屋で、内部には大小の石仏や祠が安置されており、中世以来この洞窟が山岳信仰の霊場・修行場でもあったことを物語っています。頼朝伝説と結びついたことで、湯河原の山岳霊場としての性格は一層強まり、以後も地域の人々によって石仏の奉納や伝承が受け継がれてきました。
修験者・山伏の往来と修行の実態
伊豆・箱根エリア(湯河原を含む)は、関東山伏発祥の地とも言われ、古くから修験道(山岳信仰)の行者たちが行き交った土地です。伝説によれば、修験道の開祖役行者(役小角)は文武天皇3年(699年)に伊豆大島へ流罪となった後、海上を飛行して熱海の走湯山(現・伊豆山)に渡り、この地で修行を重ねたと伝えられます。ちょうどその頃、走湯山を含む日金山(箱根外輪山の一部、十国峠付近)に修験道が定着したとも語られ、伊豆山神社(走湯権現)や箱根権現の草創説話と結びついています。史実の面から言えば、関東における組織的な修験道の展開は鎌倉時代(13~14世紀)頃と推定されますが、それ以前から伊豆・箱根には「遠くからやって来た神仙が開いた」という類の霊験譚が複数伝わっており、こうした伝承が修験者の宗教的往来を正当化し後押ししてきました。
湯河原~箱根外輪山の古道も、修験者たちの重要な行場・通り道でした。熱海の伊豆山権現で修行し、後に富士山麓の村山修験を開いたとされる僧・末代上人は、その伝説によれば日金山(十国峠)で修行を積み、富士山に数百回登拝して山頂に大日寺を建立、中世に富士山の山岳仏教(富士修験)を定着させたといいます。日金山山頂近くには末代上人の宝篋印塔(供養塔)が残されており、往時の修験者の足跡を今に伝えています。

また、この古道沿いには石仏や石塔が数多く祀られており、十国峠~岩戸山~湯河原方面へ至るルート上には江戸期に奉納されたと見られる「丁目石(ちょうめいし)」が点在しています。例えば日金山東光寺付近では石仏群の中に三十七町目・三十八町目…と刻まれた道標が確認でき、湯河原側からの登拝路にも三十九町目、四十二町目の石標が現存しています。これは山伏や信徒たちが一定間隔ごとに経文を唱えながら登拝した名残であり、当時この古道が宗教的巡礼路として整備・利用されていた証拠と言えるでしょう。
修験者の具体的な修行の場としては、前述の「しとどの窟」が挙げられます。岩壁に穿たれた天然の洞窟であるこの窟は、内部に地蔵信仰・観音信仰・弘法大師(空海)信仰に関わる石像群が安置され、長年にわたり山伏や行者が籠もり行を行った「行場(ぎょうば)」であったことが窺えます。付近には滝行に適した瀑布もあり、修験道の修行体系(瀧行、洞窟内での冥想、読経など)を行う場が一通り揃っていたようです。修験者たちは湯河原の谷深くからこの古道を辿り、滝で身を清め、洞窟で祈念し、尾根上の霊場へ至るという修行を重ねたと考えられます。現代でも湯河原町内には「関東修験道発祥の地」の伝承を顕彰し、山伏と歩くリトリート企画が催行されるなど、往時の修験の道を見直す動きがみられます。このことは、古道が単なる交通路に留まらず修行と霊場巡礼の舞台であった歴史が、地域に深く刻まれている証と言えるでしょう。
古道と峠の宗教的意義(結界・浄化など)
湯河原から箱根外輪山への道程は、地理的にも精神的にも「此岸から彼岸へ」移行する境界として位置づけられてきました。箱根外輪山の稜線は相模国と伊豆国の国境でもありましたが、霊的にも俗界と霊域を隔てる結界(けっかい)的な意味を持っていたと考えられます。古来、箱根山(箱根権現)や伊豆山権現は源頼朝をはじめ武家や庶民から厚く信仰され、「二所権現」として対で崇敬されました。これら霊山の外縁にあたる峠や山稜は、一種の聖域の門戸であり、そこを越えて山中へ入る行為は日常圏から霊的世界への踏み入りと見做されたのです。
そのため、このルート上では入山に際して身を清め、邪気を払う「浄化」の習俗が重んじられました。修験道では山に入る前に水浴や沐浴で心身を浄める「垢離(こり)」の行を行いますが、湯河原は幸い豊富な温泉に恵まれていました。密教思想では万物に仏性が宿るとされ、山伏たちは温泉の湯を聖なるものとして利用しました。すなわち、湯河原の湯そのものが修行の一環としての「湯垢離場(ゆごりば)」だったのです。実際、日本各地の温泉には役行者や弘法大師による霊験譚が付きものですが、湯河原でも白鳳期に加賀国の二見氏が当地に逃れ、霊峰白山権現の分霊を勧請して五所神社を創建したとの伝承があります。霊山白山の信仰(山岳修行)と温泉地湯河原の習合は、火山の恵み(湯)に対する畏敬と感謝を背景に成立したものと考えられます。このように、湯河原から峠にかけてのルートは、温泉で禊を行い聖なる山域に入るという浄化のプロセスを担い、峠そのものが聖俗の境界=結界となって、修験者たちの精神世界を支えていたのです。
箱根山や伊豆七島の火山信仰では、噴気や湯煙など自然現象に神仏の御業を見出す例が多くみられます。伊豆走湯山(伊豆山権現)では役行者が海岸に立ち上る五色の霧(温泉の湯煙)を発見し、霊湯を開いたという物語が伝わり、箱根山でも大涌谷の噴気地帯が地獄・極楽に喩えられて信仰の対象となりました。湯河原の古道沿いにある岩戸山(標高734m)もまた、「岩の戸」の名が示す通り霊妙な岩窟伝説を感じさせる山です。その山頂付近は安山岩質の溶岩流で巨岩がゴロゴロと露出し、「まさに修験者が好みそうな雰囲気」と評される特異な景観を呈しています。こうした岩場や巨石も結界や磐座(いわくら)的な意味を帯び、修験者にとっては神仏の宿る場所、祈りを捧げる地点であった可能性があります。
湯河原温泉文化と修験道(湯垢離場・温泉信仰)
湯河原温泉は古来「薬師の湯」「傷の湯」として知られ、湯治場として多くの人々を惹きつけてきました。その起源には宗教者の関与も指摘されます。日本各地の温泉伝説では、奈良時代の僧や修験者が温泉を発見した例が多々あり、修験者は諸国行脚の過程で各地の霊泉を開湯し、温泉信仰を広めた存在でもありました。奈良時代の高僧・行基による開湯伝説では、行基が東国巡礼の途上で病の乞食を湯河原の温泉に浸して介抱したところ、その乞食が黄金色の薬師如来に姿を変え「我は温泉の行者なり」と名乗り、湯を衆生の治療に役立てよと告げたといいます。また、上述した役行者・二見加賀之助の伝承に見られるように、温泉と山岳信仰の結びつきが早くから生じています。温泉地に山岳修行の神を勧請した背景には、温泉の霊験を仏教的に位置付け、湯の効能を信仰と結びつける意図があったと考えられます。
修験道の世界では「温泉そのものが聖地」となることも珍しくありません。専修大学の研究によれば、日本各地に「温泉聖地」とも言える霊場が存在し、そこでは温泉・湯治場と神社・寺院、地蔵・観音・薬師信仰などが複合して独特の文化圏を形成しています。なかでも仏教と温泉を密接に結びつけたのは修験者であり、彼らの背景にある密教思想では温泉の湧出も仏の恵みと捉えられました。湯河原温泉も同様に、湯そのものへの信仰が篤かったと推察されます。湯河原には薬師如来を祀る寺社や湯権現の伝説は確認されていませんが、湯の霊力を象徴するものとして「惣湯(そうゆ)」があります。湯河原では江戸時代に温泉の源泉管理を行う「惣湯滝之湯」が設けられ、地域の共同浴場かつ祈雨・豊作祈願など村の祈祷所的な役割を果たしました。これは温泉を地域の守護とみなす温泉信仰の一端といえます。修験者たちもこの惣湯を利用し、湯垢離によって身を清めつつ、温泉の癒やしを修行に取り入れていたことでしょう。
実際、湯河原町宮下には「不動堂」という堂宇があり、ここには修験者が常駐して村人のために加持祈祷を行っていました。特に雨乞い行事が有名で、深夜に修験者が鬼面(お面)を持って千歳川の祠まで下り、川水にその面を浸してから不動堂へ戻ると不思議と雨が降ったと伝えられます。この「雨乞い面」(湯河原町指定文化財)は現在も不動堂に残され、その鬼面はカエルの顔貌を取り入れ雨神を表現したものです。農耕に欠かせない雨をもたらす儀礼に温泉地の修験者が関わっていたことは、湯河原における温泉信仰と修験道の結びつきを端的に示しています。温泉の熱と水は豊穣をもたらす霊力と見なされ、修験者はその仲介者として地域社会に貢献していたのです。
さらに視点を広げると、伊豆半島全体に「伊豆修験」と呼ばれる修験道の流派・文化圏が存在しました。近年の研究(國學院深澤太郎氏)によれば、中世後期~近世にかけて伊豆半島には「伊豆辺路(いずへじ)」と称する一周巡礼的な修験道ルートがあり、湯河原(熱海伊豆山)から伊豆半島東岸を南下し下田まで至る古道が機能していたといいます。湯河原温泉もこの伊豆修験ネットワークの北端拠点として位置付けられ、温泉の霊力と結びついた修験道修行が展開されていたことは確実でしょう。
現代に息づく文化景観
日金山東光寺と十国峠の信仰・景観保全
箱根外輪山の一角に位置する日金山(ひがねさん)東光寺は、湯河原・熱海・函南(三島)から登る参詣道の合流点にあり、古来より霊山として信仰を集めてきました。日金山は「あの世に近い山」とされ、死者の霊が集まる場所との伝承から、現在でも春秋の彼岸には多くの参詣者が東光寺を訪れ、卒塔婆供養を行っています。東光寺の本尊は延命地蔵尊で、地獄で苦しむ霊を救うと信じられてきました。この地蔵信仰の霊場としての性格は現代にも受け継がれており、境内には無数の小さな地蔵石仏が奉納され、先祖供養や水子供養の祈りが捧げられています。地域住民のみならず、都市部からの参拝者も訪れており、東光寺は近年「伊豆半島ジオパーク」のジオサイトの一つにも認定されました。これは日金山の地質学的価値とともに、歴史的・文化的価値にも光を当てる取り組みであり、霊場の景観と環境が一体となって保全されています。
東光寺の山頂一帯から十国峠(標高776m)にかけては、かつて修験者や参詣者が歩いた行者道が伸びています。この日金山への参詣道(通称「日金道」)は、現在では湯河原・熱海側から気軽に登れるハイキングコースとして整備され、人気です。十国峠の山頂まではケーブルカーも運行されており、多くの観光客が雄大な富士山や相模湾の眺望を楽しみに訪れます。山頂付近には東光寺への参道も整備され、信仰の場と観光スポットが共存する形になっています。十国峠の名称が示す通り、晴天時には遠く伊豆・駿河から相模・武蔵に至る十国を見渡せる絶景が広がり、その景観は地域によって良好に維持・管理されています。また、峠付近には江戸時代の石仏群や供養塔が点在し、地元有志により案内板が設置されるなど文化財としての保護も図られています。
行者の道の現代的価値
古道や行者道そのものも、現代において新たな文化的価値を持つ資産として見直されています。険しい山道も、視点を変えれば地域の歴史と自然を体感できる「野外博物館」のような存在です。湯河原〜箱根外輪山にかけての古道は、その好例と言えるでしょう。先述の「石仏の道」と呼ばれる湯河原側から日金山への登山道には、一町ごとに奉納された地蔵尊が配置されており、山岳信仰の道標として機能してきました。この道は明治以降、一時は忘れ去られかけましたが、昭和後期から平成にかけて郷土史家や山岳愛好家によって再発見・整備が進められました。現在では神奈川県と静岡県の県境ハイキングコースとしてガイドブックにも掲載され、沿道の石仏群は歴史遺産として紹介されています。登山口や分岐点には道標や説明板が設置され、迷うことなく古道を踏破できるよう配慮されています。これにより、かつて修験者や庶民巡礼が歩いた霊場への道が、現代の私たちにとっても身近な文化体験の場となりました。山道を歩きながら信仰の歴史に思いを馳せることで、単なる娯楽としての登山が地域の文化への理解を深める機会にもなっているのです。
さらに、これら古道は地域の環境教育やエコツーリズムの資源としても活用されています。地元の小中学校では総合学習の一環で郷土の歴史散策を行い、行者道を実際に歩いて文化財を見学するフィールドワークが取り入れられています。また、有志のガイドによる歴史ハイキングイベントも開催され、参加者が石仏に手を合わせつつ峠を目指す催しは人気を博しています。こうした活動は、古道が単に昔の遺物ではなく「現在進行形の文化資源」であることを示しています。
地域による文化遺産の保存と活用
歴史的偉業や伝承を題材にしたイベントは地域おこしを兼ねて盛んです。毎年4月には「土肥祭」として、源頼朝の旗揚げに協力した土肥実平を称える武者行列が町内で再現されます。鎧武者に扮した市民や俳優が練り歩く光景は圧巻で、頼朝が敗戦から立ち上がる場面を演出する中で、実平の館が焼かれた故事を「柴灯護摩」の炎に見立てる演出も行われます。燃え盛る火を前に舞われる「焼亡の舞(じょうもうのまい)」は、修験道の護摩祭と武者の出陣を重ね合わせた勇壮なもので、郷土色豊かな無形民俗文化財として湯河原町により保護・支援されています。
そのほか、文化財の保存活用計画に基づき、行政による史跡整備や情報発信も進んでいます。湯河原町教育委員会は文化財マップを作成して石仏群や史跡の場所・由来を解説し、公式ウェブサイトやパンフレットで公開しています。観光ボランティアガイドも組織されており、希望者には古道巡りや社寺巡礼の案内をするサービスが提供されています。ガイドの養成には郷土史家や民俗研究者が協力し、単なる観光案内に留まらない学術的な知見も取り入れられています。例えば修験道の歴史や仏像の意味などを丁寧に解説することで、参加者の理解を深める工夫がなされています。近年では、箱根ジオパークや日本遺産認定の動きとも連携し、この地域の自然と文化を統合的に保存・活用する取り組みも見られます。山岳信仰の景観を将来にわたり持続的に保全するため、自然保護と文化継承を両立させる仕組みづくりが模索されているのです。
以上のように、湯河原〜奥湯河原〜箱根外輪山の古道と周辺地域に息づく文化景観は、過去から現代への連続性の中で守られ、変容し、そして新たな価値をもって活用されています。それらは単なる遺物ではなく、地域のアイデンティティそのものとして人々の暮らしに溶け込み、現代の私たちにも多くの示唆と安らぎを与えてくれます。先人たちが築いた信仰と景観を未来へと手渡していくことが、地域の誇り高き使命であり続けているのです。
まとめ:海から山へ続く祈りの道
湯河原から箱根外輪山へと続く道筋は、単なる交通路ではなく、太古から人々の祈りと暮らしを運ぶ道でした。
砂嘴に囲まれた海辺の祭祀場では、航海や漁の安全を祈り、山の頂では天候や豊穣を願って神を迎えました。両者を結んだ古道は、漁師や農民、修験者、旅人を乗せて、海と山・聖と俗を行き来する往還となりました。
修験道の峠越えや温泉での湯垢離、洞窟や滝での修行は、自然と人の営みが溶け合う信仰世界を形づくりました。そしてその営みは、時代とともに形を変えながらも、石仏や社、年中行事、景観として今に受け継がれています。
現代の私たちがこの道を歩くとき、足元には縄文の貝塚、古墳時代の祭祀跡、中世の行者道といった、幾千年の歴史が折り重なっています。海と山をつなぐこの道は、過去から未来へ続く一本の糸のように、地域の記憶と誇りを紡ぎ続けています。

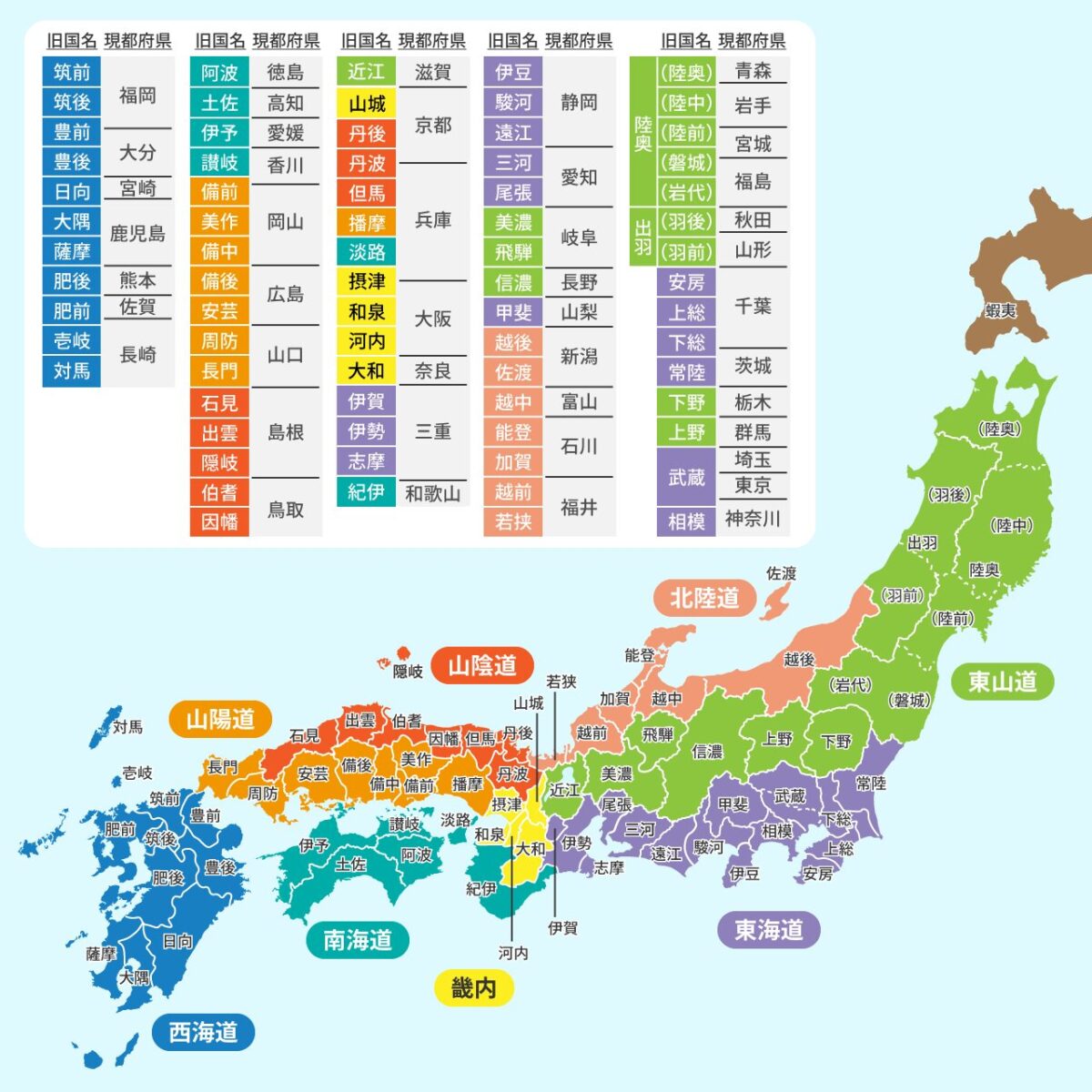
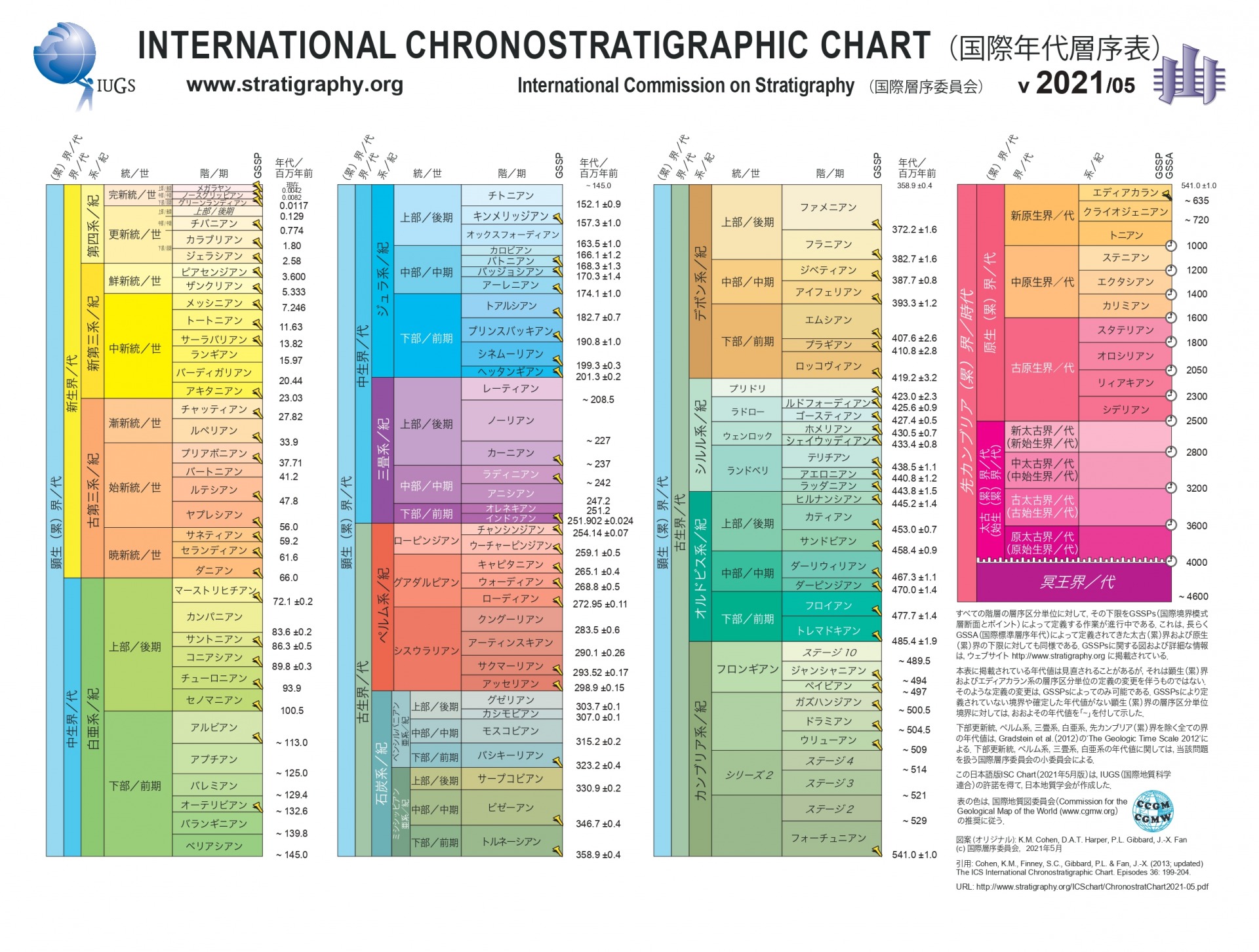


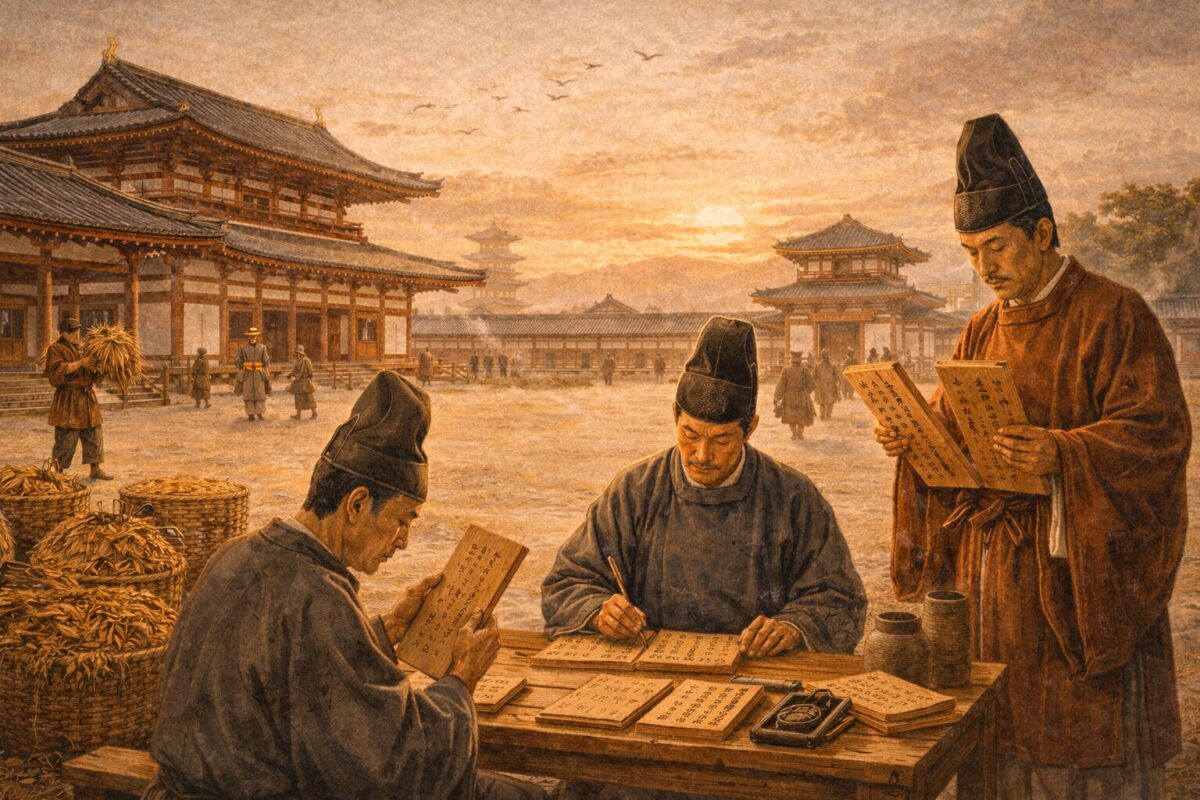

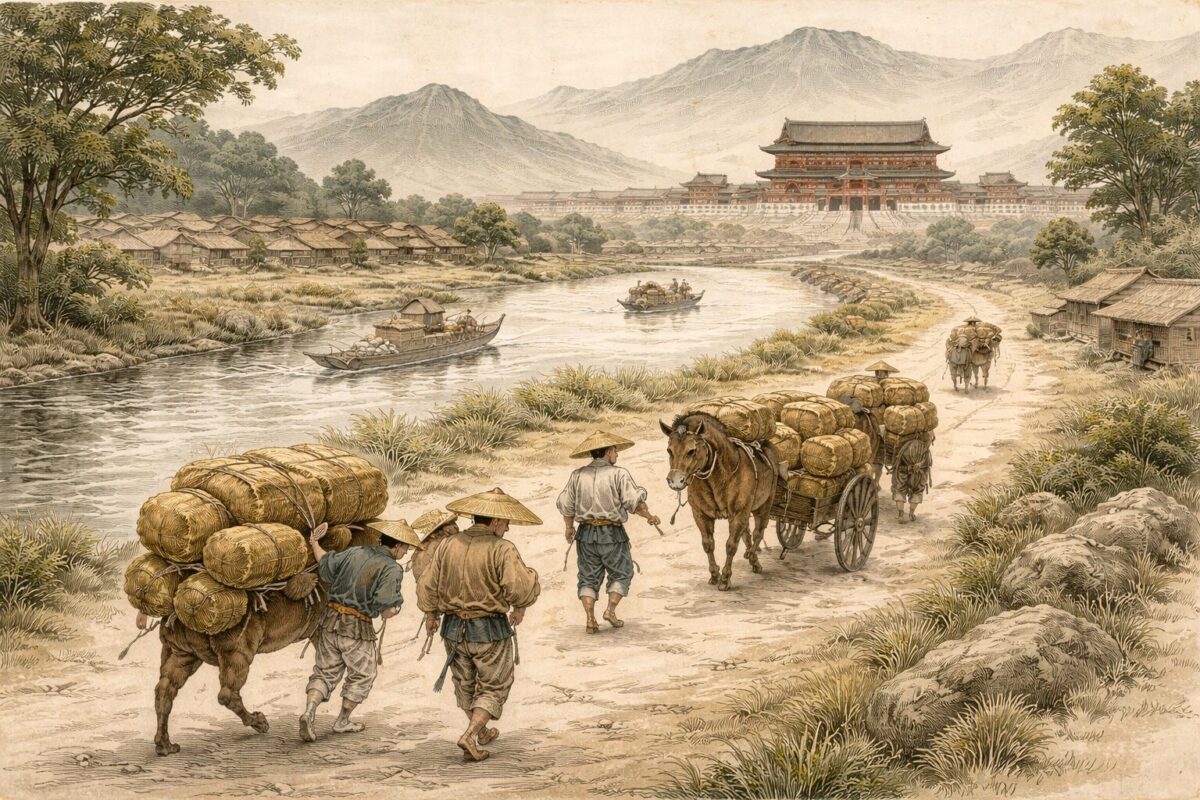


コメント