


仏教伝来
仏教伝来の時期については諸説あるが、教科書的にいえば538年に仏教が百済から日本に伝わったとされている。
仏教との関わり方について、蘇我氏(仏教を積極的に受け入れる派)と物部氏(日本古来の神を尊重する派)の間で争いが起こったというのが、私も含めて一般的な認識だと思う。しかし調べてみると、そう単純な話ではない、と思わされる見解を知った。
仏が「他国神」とか「蕃神(あたしくにのかみ)」とか記録にあるように、日本の神と同じレヴェルでみられていたことは誤りあるまい。
新潮文庫 日本仏教史 思想史としてのアプローチ 末木文美士
一体、日本の神は「何にまれ、尋常(よのつね)ならずすぐれたる徳(こと)のありて、可畏(かしこ)きもの」という本居宣長の定義にあるように、人知を超えた恐ろしい存在と考えられ、人びとに恩恵を与える一方、その怒りは人びとに厄災をもたらすと信じられていた。
かつまた、神は外からやってきて人びとのところに定住しないと考えられていたから、新しくやってきた仏なる存在がそうした「客人神(まれびとがみ)」として受け取られたとしても不思議はない。
崇仏排仏の争いがあったとするならば、崇仏側が仏を招福神とみたのに対して、排仏側はそれを厄災神と考えた、とみることもできよう。
しかし、当時「国神」対「他国神」「蕃神(あたしくにのかみ)」という民族意識や国家意識に基づいた対立があったかどうかは疑問であろう。
ともあれ突然やって来た客神は得体の知れない存在であり、上述のように、まず恐るべき存在とみられたであろう。
とするならば、たとえ在来の神の怒りを招くという理由で排仏を主張したとしても、ただやたらに仏像を壊したり、投げ捨てたりはできないはずである。
その場合には丁重に歓待したうえでもとの地に帰っていただくのが神に対する礼である。
依代を焼いたり水に流すのもこうした儀礼の一環であり、仏像の廃棄もこうしてみるとそれなりの意味が納得できる。
神道史の研究家西田長男は、崇物側が客人神を迎える役目であったのに対し、排仏側がそれを送り出す役目を分担したとみているが、あながち荒唐無稽な説ともいえないように思われる。
なお、このようにみるならば、仏像は当然依代にあたるものになるが、それが人間的な姿をとっているのは不可思議な感を与えたであろうし、のちに日本の神がしだいに人格的な個性をもつようになるのも、こうした仏教の影響があったのではないかと推測される。
上記を要約すると、仏は外からやってきた神様であり、当時の日本人からすれば
得体のしれないものであって、まず最初に恐怖があったのではないか、ということが書かれている。
当時の日本人(倭の人間といった方が良いだろうか)が、突然やってきた仏という存在に対して、どんな想いを巡らせたか想像させられ非常におもしろい。
保守的な人間であれば、まるで黒船襲来のような恐怖を感じたであろう。
あるいは感受性が高い人にとっては、仏に秘められた神秘性に共鳴しただろう。
教科書的な崇仏・廃仏の対立という単純構図ではなく、むしろ外来の神に対する扱い方に迷った人々の葛藤という方が当たっているかもしれない。
神と仏の関係性
さて、神仏習合というテーマについて考えていく中で、まずは仏教伝来時について掘り下げてみたが、次に、日本の神と仏の関係性が時代とともに、どのように変遷していったかを見てみよう。
参考にした本によれば、神と仏の関係は三つに分類できるという。
史料の中に記載されていることから関係性を探ることができるようだ。
それでは神の仏への従属はどういう形態をとったであろうか。
新潮文庫 日本仏教史 思想史としてのアプローチ 末木文美士
それには次のような三つの形があったと考えられる。
1:神は迷える存在であり、仏の救済を必要とするという考え方。
2:神は仏法を守護するという考え方。
3:神はじつは仏が衆生救済のために姿を変えて現れたのだという考え方。
1、2が奈良時代からはじまるのに対し、3はやや遅れてはじまる。
まず第一の形態をみてみよう。
この典型的な例はいわゆる神宮寺にみられる。
その初出は『続日本紀』文武天皇二年(六九八)に「多気大神宮寺を度会郡に遷す」とある記事であるが、これは「寺」のないテキストもあり、そのほうがよいとみられている。
それを除くと、早い例は霊亀(七一五-七一七)の頃、藤原武智麻呂が神託によって越前(福井県)の気比神宮に神宮寺を建てたという『藤原家伝』の記事、および養老年中(七一七-七二四)に若狭比古神宮寺が建てられたという『日本逸史』所引『日本後紀』天長六年(八二九)三月十六日条の記事である。
前者によると、神が武智麻呂の夢に現れ、「幸いに吾が為に寺を造り、吾が願を助け救え。
吾れ宿業(すくごう)に因(よ)りて神たること固(もと)より久し。
今仏道に帰依し、福業を修行せんと欲するも、因縁を得ず。
故に来りて之を告ぐ」と言ったので、さっそくに武智麻呂が神宮寺を建立したというのである。
後者も同様で、神が仏法に帰依したいがそれを果たさないために祟りをなし、そこで寺を建てたというものである。
これらの記事では、神は仏によって救われるべき存在とみられている。
インド以来の仏教の見方では、インドの神々(天とよばれる)はいまだ六道の一つで、輪廻の苦の枠内にとどまる存在である。
それと類比的に日本の神も考えられたものである。
上記によれば神と仏の関係性は3つに分類されているようだ。さらに調べてみると、分類には以下の名称が付けられている。
- 神身離脱説 (神は迷える存在であり、仏の救済が必要という考え方)
- 護法善神説 (神が仏を守護するという考え方)
- 本地垂迹説 (神というのは、仏が姿を変えて現れた存在であるという考え方)
日本の神といっても色々あるので一概には言えないように思うが、神が仏の救いを求める描写があるようだ。
神宮寺の考え方として、神が仏を護るという構図と思っていたので意外だった。
神が迷える存在と考えられていたとすれば、当時の人の感覚として、神というのは人間と非常に近いものと捉えられていたのだろうか。
このあたりはもう少し詳しくみてみたい。
第二の形態は神が仏法を守護するというものであるが、その初出は、天平勝宝元年(七四九)に宇佐八幡宮の託宣があり、大仏建立を援助するために上京したという『続日本紀』の記事である。
新潮文庫 日本仏教史 思想史としてのアプローチ 末木文美士
このことは大仏建立を国の総力を挙げての大事業として印象づける大きな宣伝効果をもったにちがいない。
土着の神が仏を助け、仏法を守護するというのは、インドの梵天や帝釈天以来の護法神という考え方で、やはり広くみられるものである。
八幡神はもともと北九州の神で海の神とも銅山の神ともいわれるが、とくに応神天皇の霊と習合して勢力をもつようになっていった。
それがいち早く仏教との関係を強めたわけで、平安初期には「八幡大菩薩」と菩薩号を得、また僧形八幡の神像が造られるなど、仏教徒の関係がきわめて緊密な神である。
大仏建立に際しては、その苦役ゆえに民衆のモチベーションを保つことが難しかったといわれているが、そういう状況の中で、神様が助けてくれていると考えるようになったのだろうか。
当時の民衆の中で、地域によると思われるが、神と仏、どちらが親近感のある存在だったのだろうか。
個人的には、おそらくは神の方が親近感があったのでは、と思わされた。
第三の形態は神仏を一体ととらえるもので、最も進んだ神仏習合の形を示している。
新潮文庫 日本仏教史 思想史としてのアプローチ 末木文美士
すでに奈良時代の大仏建立に際して、天照大神であるところの日輪は大日如来、盧遮那仏であるとの伊勢神宮の神託があったともいわれる。
ただこれに関しては史料的に問題があり、なお検討を要する。
確実な史料では、平安中期になると「権現」「垂迹」などの語がみられ、本地垂迹的な発想が明確になってくる。
さらに平安後期からしだいに、どの神がどの仏の垂迹であるかということが個別的に確定してゆく。
例えば、熊野三社は阿弥陀・薬師・観音、日吉(ひえ)は釈迦、伊勢は大日というような具合である。
ところで本地垂迹というのは、いうまでもなく、本地、すなわち本来のあり方をしている仏が、垂迹、すなわち仮の姿をとって応現したのが神だという考え方であるが、「本迹」という概念は、もともと中国の道家系思想に発するもので、仏教ではとくに天台の『法華経』解釈において重視された。
すなわち、『法華経』の前半部、歴史上の釈迦仏の説法を伝える箇所が「迹門」、それに対して後半部の永遠絶対の仏の出現を説く部分が「本門」と呼ばれるのである。
平安期には天台が仏教思想として最も大きな影響力をもったことを考えると、本地垂迹説の発展にもこの天台の発想が大きく寄与したのではないかと思われる。
神仏習合といえば本地垂迹説と考えていたが、ここでようやく登場。この考え方のはじまりとして確実なものは、平安中期とのことで、第一、第二の考え方に比べるとやや遅い。
また、天台の仏教思想が影響したというのも非常に面白い。
本地垂迹によって、神と仏の対応関係を付けていくようになるが、矛盾を生じるような関係もあるように思う。
このあたりを掘り下げてみていくのも面白いのではないだろうか。
本地垂迹説の浸透
仏教伝来時における崇仏・廃仏の対立(必ずしも対立していたかどうかは議論が分かれる)からはじまり、神と仏の関係性について詳細に論考されている本の内容を上記では書いた。
そのなかで第三の形態として
本地垂迹説(ほんぢすいじゃくせつ)について述べた。
本地垂迹とは、いま目の前に現れている神は、仏が人々を救済するために姿を変えて現れている、という考え方であった。
さて、本地垂迹の考え方が浸透した後、鎌倉時代に入ると鎌倉仏教の影響により神祇不拝で良いとする仏教徒が出てきた。
さらにその動きを批判する旧仏教側の主張も激しいものがあったようだ。
この旧仏教側の主張が、まさに本地垂迹を基にしていることに注目したい。
興福寺の僧 貞慶(じょうけい)の例を以下に示す。
本地垂迹説がその教理的体系を整えるのは平安中期のことである。
広神清 1997「日本における神道理論の形成」哲学・思想論叢p1-18
鎌倉時代に入ると、仏教界ではいわゆる鎌倉仏教が隆盛となって、その教理のゆえに神祇不拝を唱える仏教徒が目立ってくる。
その典型的な例が浄土教徒の場合である。
浄土教では、阿弥陀仏に信心を集中し南無阿弥陀仏の念仏を専修することにより、阿弥陀仏に導かれて西方極楽浄土に救いとられると説く。
救われるためには阿弥陀仏が唯一の信仰対象である(弥陀一仏への帰依)から、神祇は信仰の対象としなくてもよい(神祇不拝)ということになる。
この神祇不拝の立場を批判したのが、それまでの仏教の伝統を保持するいわゆる旧仏教側の論理である。
奈良の興福寺の僧貞慶(1155~1213)は、専修念仏の宗義の糺改を朝廷に請う上奏文「興福寺奏状」の中で、専修念仏の教理を次のように批判する。
「念仏の輩、永く神明に別る、権化実類を論ぜず、宗廟大社を憚らず。もし神明を恃めば、必ず魔界に堕つと云云。実類の鬼神においては、置いて論ぜず。権化の垂迹に至っては、既に是れ大聖なり、上代の高僧皆以て帰敬す。(中略)」
ここに見られるように、貞慶の専修念仏批判の理論的根拠は本地垂迹説である。
専修念仏の教徒が、日本の神々を礼拝せず、もしこれらを礼拝すれば地獄に堕ちると説くのは、念仏教義の過失であると言う。
なぜならば、日本の神々は仏・菩薩の権化であり垂迹であるからである。
この過失を貞慶は「霊神に背く矢」と言うが、日本の神々が霊神として尊崇すべき存在であることの根拠は、神々が神々であることに置かれているのではなく、それがまさしく仏・菩薩の垂迹であることに求められるのである。
日本の神々をないがしろにする新仏教徒に対抗して、神々の尊貴である所以を、それらが仏・菩薩の応現・垂迹である点に求める旧仏教の側からの神々の位置づけの主張が、いわゆる仏家神道である。
貞慶の鎌倉仏教批判はまさに、本地垂迹という神仏習合が背景にあると言えるだろう。
当時の旧仏教側の神と仏に対する見方をうかがうことができる。






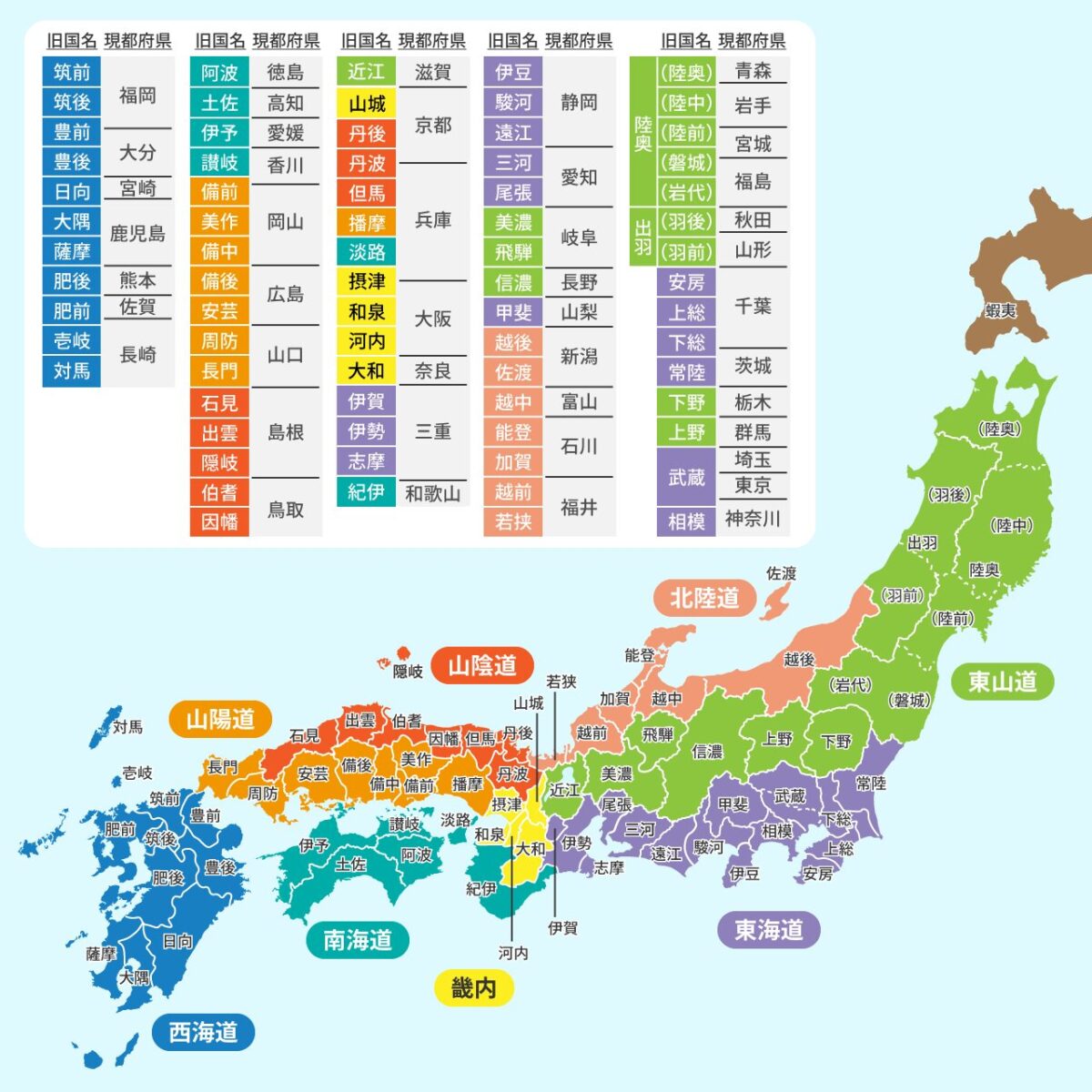
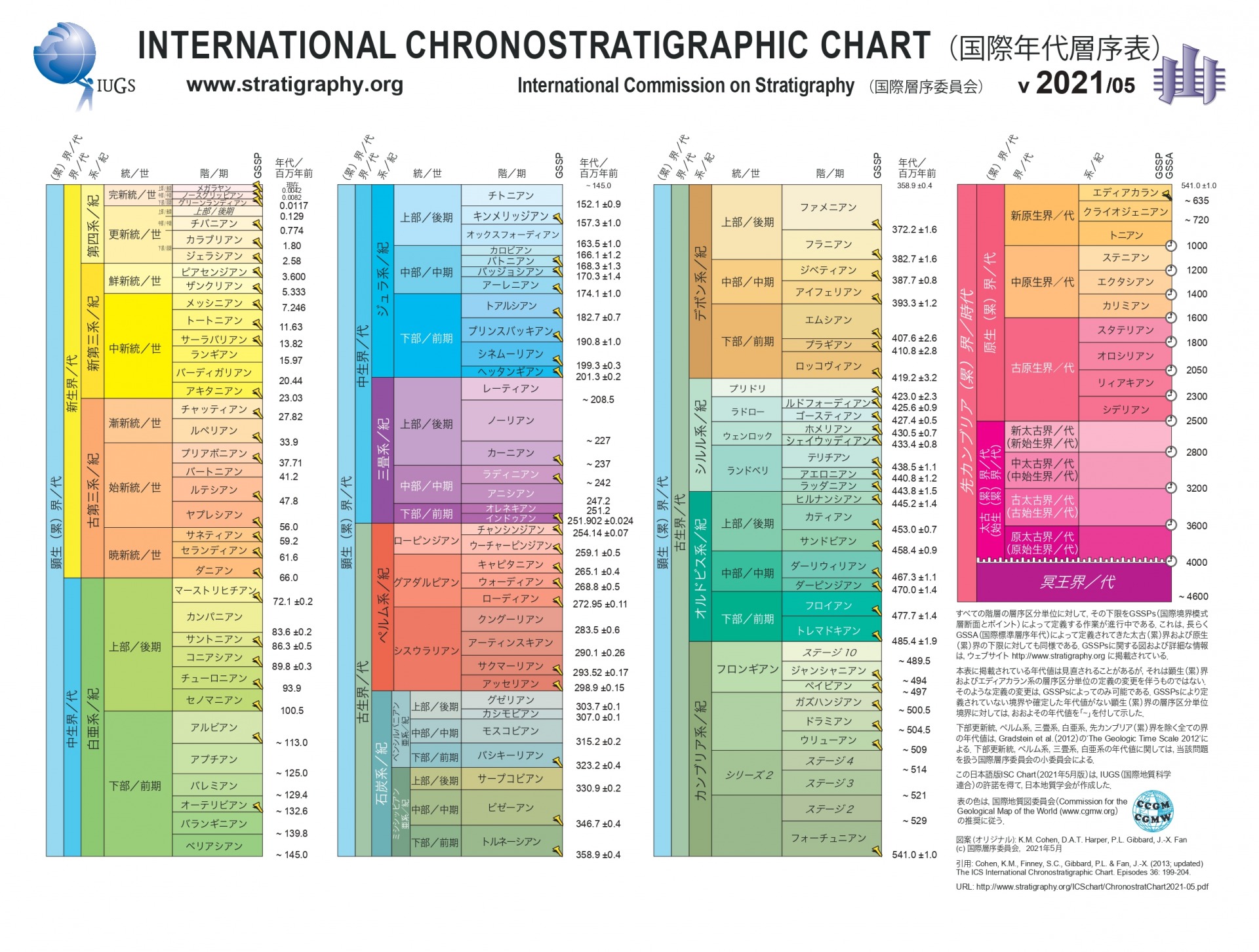







コメント